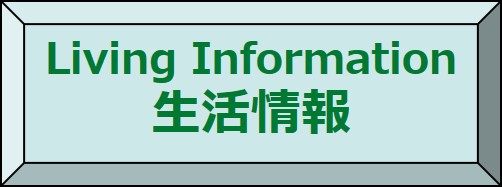■ 代表挨拶

代表理事 山辺 真理子
2006年に20人足らずの市民ボランティアで設立した団体が、2023年6月現在240人の会員の皆様に支持されるNPO法人に育ちました。様々な文化的背景を持つ人たちがお互いを認め合い、関わり合いながら暮らしやすい地域をつくる、すなわち多文化共生の地域づくりが私たちの願いです。
2020年から世界を分断してきた新型コロナの感染が落ち着き、人々の移動が活発化している中で、西東京市の外国人人口は今後も増加すると見込まれています。NIMICは、「支援、交流、活動の活性化」という3つの柱で動いています。支援の中心は多文化共生センターでの日常生活相談(市の委託事業)と子ども日本語教室4か所の運営(自主事業)です。交流の重要性は、料理や音楽が多様な文化交流で豊かになっていることを見れば明らかです。異質なものとの出会いが相互理解に進むには、実際に会ってともに時間を過ごすことが重要だと考えます。そのために、NIMICは年間を通して交流のための自主事業を展開しています。様々な事業は多くのボランティアに支えられていますが、ボランティアの発掘・育成のために3つ目の柱である活性化事業として、講座や広報活動にも力を入れています。
同じ地域に暮らす隣人として、できることを持ち寄り助け合って暮らす社会の創出に向けてともに活動しませんか。色々な世代の方々、思いを同じくする方々とともに持続可能な活動を創っていきたいと思います。
■NIMICの生い立ち
NPO法人西東京市多文化共生センター(設立時名称:西東京市多文化共生・国際交流センター)は、2004年9月から西東京市長の依頼により開かれた「国際交流組織設立検討懇談会」による1年余りの検討を経て作成された提言書「多文化共生社会に向けて」の理念にのっとり、懇談会メンバーを中心として2006年3月に設立されました。2008年10月に、東京都から特定非営利活動法人の認証を受け、「NPO法人西東京市多文化共生センター(愛称:NIMIC ニミック)」として再出発しました。
2013年には、社会情勢の変化を踏まえ、これまでの成果と今後の課題をフォローアップレポート「西東京市における『多文化共生社会』の形成に向けて」にまとめました。また、2017年には、63ページの「西東京市の多文化共生この10年と今後に向けて」を作成しました。これからも公助と共助の役割分担も視野に入れ、さらに活動の充実を図っていきます。
・「西東京市の多文化共生この10年と今後に向けて」(P1-P34)
・「西東京市の多文化共生この10年と今後に向けて」(P35-P63)
■活動理念
異なる文化的背景を持つ人々が、宗教や信条、生活習慣の違いを互いに理解し尊重し合い、偏見や差別意識を持つことなく、共に地域で暮らす「多文化共生社会」を築くことで、世界平和に寄与することを目指して活動します。
「外国人*にとって住みやすい社会は、子どもやお年寄り、障がいを持つ人など、みんなにとって住みやすい社会」と考え、外国人支援、および受け入れる地域社会の啓発活動を通じて、市民活動の育成を図ります。
*一般的に理解しやすい「外国人」を使用していますが「多様な文化を持つ人々」を指します。
■キャッチフレーズ「ともに住み、ともに生きる」
NIMICは、2020年にキャッチフレーズを会員より募集し、会員投票および理事による選考を経て「ともに住み、ともに生きる」に決定しました。 ここでは、その考案者がこのキャッチフレーズに込めた想いを、ご紹介します。
| 「ともに住み、ともに生きる」 |
|---|
| 『NIMICの思いを、やさしい表現で簡潔に表現しようと心がけました。私たちは皆、それぞれの背景を持ってこの西東京市に住んでいます。「ともに住み」は、自分自身をはじめとして、あらゆる出身・国籍・宗教・人種・民族・世代・性別・障害の有無・社会的地位など多様な人々が、同じ地域にともに隣人として生活している客観的な状況を表現しています。そして「ともに生きる」には、その全ての人がそれぞれの違いを超えて、互いに認め理解し尊重し合い、協力し合って、誰もが楽しくイキイキとより良い人生を生きていける社会を築くとの主体的な決意を込めています。このフレーズが、多くの人びとにとって身近な言葉となり、込められた思いが少しでも多く実現することを願っています。』 |
NIMICでは、このキャッチフレーズにより、NIMICの活動理念をより簡潔な言葉で表現し、「with コロナ」の時代の新しい多文化共生社会をみなさまと共に創っていきたいと思います。
■SDGs(持続可能な開発目標)への貢献
NIMICは、活動理念に基づき、行政や他団体とのパートナーシップを通じて、地域における外国人生活支援など、異なる文化的背景を持つ人々誰もが、共に地域で快適に暮らせる「多文化共生社会」の実現により、持続可能な開発目標(SDGs)3、4、5、10、11、16、17の達成に貢献することを目指します。
■活動内容
1.多文化理解の促進のために
| 身近なふれあいの場づくり |
|---|
|
留学生ホームビジット、ゆかたを着て夏まつり、日本語スピーチコンテストと交流会など、身近なふれあいの場を作ります。 >過去のイベントを見る |
| 子ども向けワークショップ |
|---|
|
つながる世界プロジェクト、こども対象多言語で楽しくなど子どもの年齢に応じた外国人とのワークショップを開いています。 |
| 市民まつり |
|---|
| 世界地図歩きなどのゲームを通して、多くの人に多文化を楽しんでもらい、多文化共生の理解者のすそ野を広げます 。 |
| 多文化タイム |
|---|
| 在住外国人の協力により、お茶を飲みながら少人数で多文化について語り合ったり、外国語を学んだりします。 |
2.地域に在住する外国人支援のために
| 相談窓口運営(外国語で無料相談) |
|---|
|
月曜~金曜、午前10時~午後4時(12時~午後1時は昼休み)西東京市の委託を受け、イングビル1階の多文化共生センターで日常生活相談に応じています。 言語により通訳いる曜日が異なります。 >ご案内はこちら |
| 多言語サポート |
|---|
|
通訳ボランティアの協力の元、市報抜粋多言語版「くらしの情報」作成、相談窓口通訳、学校や市の機関への通訳派遣などを行っています(市の委託事業)。市の総合防災訓練にも協力しています。 |
| 子ども日本語教室 |
|---|
|
外国につながる小・中学生の日本語学習・適応サポート教室を小学部・中学部に分かれて毎週開講しています。市と共催のボランティア入門講座を受けたスタッフ等が研鑚を積みながら対応しており、元教員の専門性や海外子育て経験などを生かして活動する人もいます。子ども日本語教室在籍の保護者等への進学情報提供、教育相談にも通訳ボランティアの協力を得て対応しています。 >子ども日本語教室のご案内はこちらから |
3.多文化共生に向けての活動の活性化のために
| 人材発掘・育成(各種講座) |
|---|
|
市と共催で、日本語ボランティア入門講座、多文化ボランティア講座、日本語ボランティアフォロ―アップ講座など、年間を通じて開講しています。講座担当者数名が企画・運営に携わっています。 |
| 市内各団体・ グ ループの支援 ・ ネットワーク化 |
|---|
|
多文化共生を進めるボランティアや団体の支援・ネットワーク化のため、ボランティアによる日本語教室情報を掲載しています。また、要望によりフォロ―アップ講座の開講や、外部研修の紹介も行っています。 |
4.さらに大きな広がりのために
会員に対して、NIMICの活動全般の周知を図り、イベントや事業参加を募る目的で毎月メルマガ「NIMIC通信」を発行しています。また、広く活動への理解を呼び掛け、多文化共生に関する情報を提供するために、ホームページ(本サイト)とX(旧ツイッター)、Instagram、facebookを開設しています。一年間の活動全体を、手に取ってじっくり読める媒体としては、 年間活動記録誌「多文化のわ」を発行しています。
■役員
| 役名 | 名前(所掌) |
|---|---|
| 理 事 | 山辺 真理子(代表理事) |
| 理 事 | 岩野 英子(副代表理事・事業総括) |
| 理 事 | 田村 久教(副代表理事・総務総括・財務会計総括・広報総括) |
| 理 事 | 楊 智(文化担当) |
| 理 事 | 清水 智子(事業担当、財務会計担当) |
| 理 事 | 小野 千穂(事業担当) |
| 理 事 | 高橋 二朗(事業担当) |
| 理 事 | 竹村 正和(企画・総務担当) |
| 理 事 | 佐藤 泰治(事業担当・広報担当) |
| 理 事 | 加藤 祐子(事業担当・広報担当) |
| 監 事 | 久保 芳昭 |
| 監 事 | 種村 政男 |
■定款および事業報告
・定款
・事業報告
-2022年度事業報告
-2022年度貸借対照表
-2021年度事業報告
-2021年度貸借対照表
-2020年度事業報告
-2020年度貸借対照表
-2019年度事業報告
-2019年度貸借対照表
-2018年度事業報告
-2018年度貸借対照表